『財産管理契約』
判断能力があるうちに、自分の財産の管理を信頼できる人に任せる契約です。認知症などで判断が難しくなったときに備えます。
『任意後見契約』
将来、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ後見人を選び、財産管理や生活支援などを依頼する契約です。発効には家庭裁判所の審判が必要です。

INHERITANCE
相続
-
遺言
自分の死後に財産をどう分けるかを記した法的な文書です。
『自筆証書遺言』
全文を自筆で書く遺言の形式です。令和2年からは財産目録をパソコンで作成できるようになりました。
※法務局による『遺言保管制度』が令和2年から設けられました。
自筆証書遺言を法務局に保管できる制度で、紛失や改ざんのリスクを減らすことができます。
『公正証書遺言』
公証人が作成・保管する遺言で、内容が法的に整っており、紛争防止に効果的です。証人2人の立ち会いが必要です。
『遺言信託』
遺言により遺産を一定の人・機関に信託し、信託を受けた受託者が、名宛人となった受益者のために財産を管理・分配する仕組みです。単に相続させるだけでなく、使い道を定めたい場合に有効です。
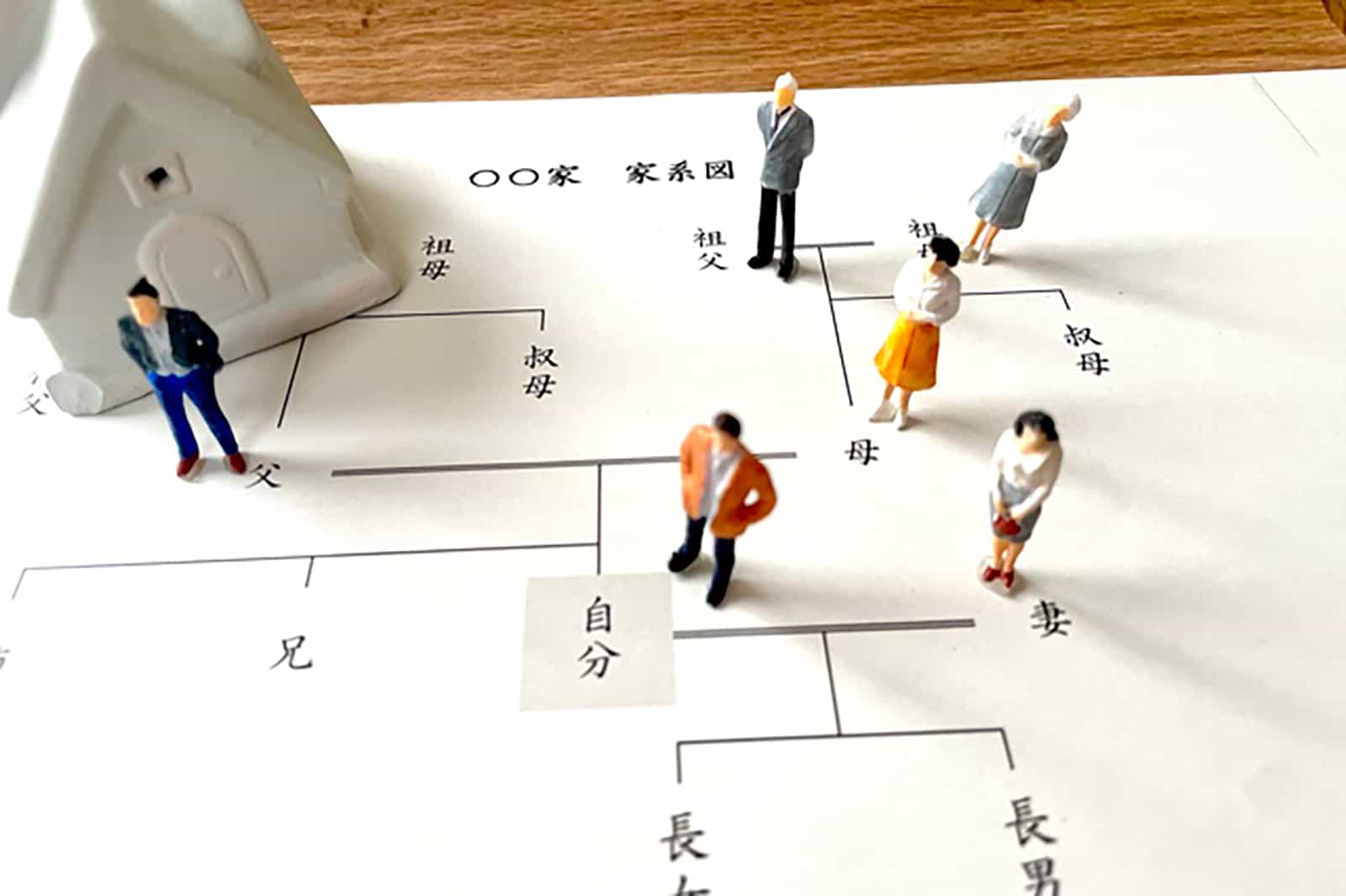
-
『遺産分割協議』
相続人全員で話し合い、遺産をどのように分けるか決める手続を行います。
*『寄与分』
被相続人の介護や家業への貢献などにより、特別に相続分が増えると認められる部分です。
*『特別受益』
生前に多額の贈与や援助を受けていた場合、その分を相続財産から差し引いて公平に分ける考え方です。
-
遺言の『検認』
家庭裁判所が遺言の存在と内容を確認する手続きです。公正証書遺言以外の遺言に必要です。
『遺留分侵害額請求』
法律で定められた最低限の相続分(遺留分)を侵害された相続人が、その不足分を請求できる制度です。
※相続税の申告、納税の問題と民法上の遺産相続は、似て非なる部分がありますので、相続税の納税ができるかどうかと相続が円満に解決するかは別問題です。
相続税の申告、納税については、提携の税理士事務所のご紹介が可能です。
※令和6年から相続登記が義務化されました。相続登記については、併設の司法書士事務所と連携いたします。
COLUMN
関連コラム
-
COLUMN2025.03.03 | Vol.274
賃借物件を解約すると「相続放棄」はできなくなるのか
【実際にあった相続相談⑥】
-
COLUMN2025.02.07 | Vol.269
葬儀費用の支出後に「相続放棄」はできるのか
【実際にあった相続相談⑤】
-
COLUMN2024.11.08 | Vol.262
死亡保険金は相続分になるのか。また特別受益とは
【実際にあった相続相談④】
-
COLUMN2024.08.29 | Vol.256
遺言書で相続人を「廃除」することはできるのか
【実際にあった相続相談③】
-
COLUMN2024.07.26 | Vol.253
「遺言書の検認」を怠るとどうなるのか
【実際にあった相続相談】
-
COLUMN2024.06.24 | Vol.250
遺言書で指定された相続人が、先に亡くなったときには
【実際にあった相続相談】
-
COLUMN2024.05.20 | Vol.248
他界した夫のかわりに、義母の介護を行ってきた女性が請求できる「特別寄与料」とは
【実際にあった相続相談】
-
COLUMN2024.04.22 | Vol.246
相続登記の義務化により、これまでと何がどう変わるのか
【身近なところのニュース法律解説】
-
COLUMN2022.03.03 | Vol.170
姻族関係終了届を出したら、 子供と亡夫の親族との関係は解消できる?
【人に聞けない相続】第7回
-
COLUMN2021.04.15 | Vol.134
教育資金の一括贈与制度って知っていますか?
【人に聞けない相続】第12回
-
COLUMN2020.12.26 | Vol.115
相続に備えてエンディングノートに書いておくべきこととは?
【人に聞けない相続】第11回
-
COLUMN2020.11.12 | Vol.111
民事信託を活用した財産承継とは
【人に聞けない相続】第10回
-
COLUMN2020.02.19 | Vol.70
相続対策の種類によって変わる確定申告時の要件や必要書類とは?
【人に聞けない相続】第9回
-
COLUMN2019.12.03 | Vol.64
争族を未然に防ぐ、遺留分を捻出できないときは
【人に聞けない相続】第8回
-
COLUMN2019.11.30 | Vol.63
親子間で不動産売買時の注意点
【人に聞けない相続】第6回
-
COLUMN2019.11.30 | Vol.62
急な資産の増加で相続税の負担が増えた時は…
【人に聞けない相続】第5回
-
COLUMN2019.11.30 | Vol.61
節税対策で孫を養子縁組にするメリット・デメリット
【人に聞けない相続】第4回
-
COLUMN2019.11.28 | Vol.60
持ち家がない人が不動産を相続すると、相続税が大幅に減少…?
【人に聞け相続】第3回
-
COLUMN2019.11.28 | Vol.59
売却 or リフォーム?相続した実家の活用方法
【人に聞けない相続】第2回
-
COLUMN2019.11.28 | Vol.58
姻族関係終了届遺族年金や相続はどうなる?
【人に聞けない相続】第1回
-
COLUMN2017.02.13 | Vol.6
相続編























